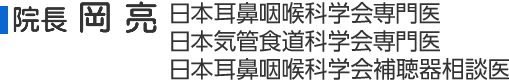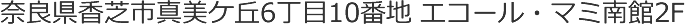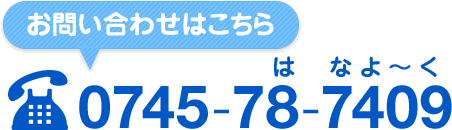医院からのお知らせ
2025.07.13
新型コロナ感染症について NEW !
7月11日奈良県感染症情報が発表されました。再び新型コロナ感染症が3位に上昇しました。ほぼ1か月間、6位以下でしたので要注意と考えます。昨年は、7月20日頃に新型コロナ感染症の患者数がピークに達し結局年間3万5000人が亡くなりました。今年はもちろん減少してはいますが入院も7人となっており警戒は必要と考えます。2025.07.13
熱中症の患者数 NEW !
7月11日に奈良県の熱中症患者数が発表されtました。7月6日時点で444人となり同時期一昨年131人、昨年236人、今年444人ですので徐々に増加しています。そのうち半分が75歳以上、男性6割、3割家の中で発生しています。住居内での熱中症の半数が、エアコンが設置されていないか、設置されていても稼働させていない部屋で発生しているとの事です。2025.06.29
熱中症の患者数
6月27日(金)奈良県の熱中症救急搬送者数についての発表によると昨年の同時期と比較して2倍の218人(昨年102人)となりました。218人のうち半数が75歳以上、6割男性、発生場所のトップは、家の中でしかも半数の方がエアコンがあっても使用していませんでした。統計的には、熱中症の患者数が最多になる時期は、梅雨明けの第一熱波到来時とのことですのでまさしく今週となります。夏に24時間エアコンをつけるのは、もはや絶対条件の様相になってきましたが当院のような耳鼻科に受診される方はむしろ冷房病の方で、熱中症には絶対ならないようにしかもクーラー病(冷房病)にもならないようにと頭の痛い夏になりました。2025.06.22
夜間の寝室でのエアコンの使用について
熱中症の発生場所として居間、リビングに次いで寝室が多く集合住宅では最上階が多い、寝室が西に面している場合が多い、という事がわかっています。また高齢者の熱中症の患者さんの大半は夜間のエアコンの利用頻度が低いという事もわかっています。ただし、一晩中エアコンを作動させるといわゆる「寝冷え」「冷房病」「クーラー病」になる可能性がありその初期症状はむしろ熱中症やコロナの初期症状にも近いために対処が遅れることもあり頭が痛いところです。とりあえず8月末まではエアコンの寝室での使用はやむを得ないと考えます。ただし、「冷房病」等を防ぐために寝室に温湿度計を置き就眠1時間前に寝室の温湿度計を計測しましょう。もしその時寝室の室温が31℃であっても就眠直前にはエアコンを使用して一気に温度23℃、湿度60%程度までに下げてしまいましょう。その後3つの方法を考えます。1.タイマーをつけずに一旦エアコンを切る。それから就眠する。夜間暑くて目が覚めるならその都度29℃、最弱風で1時間後「切り」タイマーに設定してエアコンを使用する。2.一旦エアコンを切る。次にタイマーの3時間後「入り」、4時間後「切り」を同時に設定して就眠3時間後電源が入って4時間後電源が切れるように設定する。(つまり夜間暑くなることを想定して夜間1時間だけエアコンが自動に作動するように設定する。)その際も28℃~29℃、最弱風の設定をする。絶対に風量自動を使用しない。その後就眠する。ただし、これはエアコンによってはできない機種もあり昼間に実際に試してください。3.そのまま29℃最弱風で一晩中つけておく。以上3つの方法を考えますが1は「寝冷え」にはならないと思いますが熱中症には用心しなくてはなりません。2.は機種によっては不可能な場合もあります。3.は熱中症にはなりませんが「寝冷え」になる可能性がありこれで当医院に受診される方が多いです。どの方法も冷風が直接特に顔に当たらないように気を付けてください。2025.06.22
熱中症について
6月19日、80代の女性が大和郡山市内の畑で熱中症のため死亡されました。昨年は、発見日に死亡された方はいませんでしたが2023年7月26日、また大和郡山市の畑で70代の男性の熱中症による死亡が確認されています。今年は1か月早いことに注目です。いままで熱中症の患者数の増多は、梅雨明けの第一熱波時となっていました。その後、暑熱順化によって徐々に高温に体が慣れていき8月中旬に向けて気温が上昇しても熱中症の患者数は減少していきます。今年、救急搬送患者数が昨年より15人多いことや6月に死亡者が出たことでさらなる注意が必要です。2025.06.15
熱中症について
6月16日(月)から一気に気温が上昇し今まで朝、夜は幾分涼しい時間もありましたがこれからは早朝で28℃の気温となるそうです。また令和6年度の熱中症死亡者数の確定値が出ていない為、令和5年度の各都道府県別の熱中症死亡者数を見てみると熱中症死亡者数1651人中、最多死亡者数が北海道で105人でした。この年新潟62人、青森県51人、秋田県44人です。対して南方の沖縄県、鹿児島県は15人でした。もちろん東京都290人、大阪府137人と都市部は多いのですが日本の北方が比較的死亡者数が多いのには何か理由がありそうです。今までの経験から熱波に対して対処が遅れたのかもしれません。令和6年はどうだったのでしょうか。確定値が出ましたらご報告いたします。ちなみに奈良県は、4人で全国で一番少なかったです。2025.06.08
新型コロナ感染症について
2020年新型コロナ感染症が奈良県でも発生し5位以内に感染者数が上昇してから先週初めて6位以下となりました。ただし今も1歳以下と10歳以上(80代以上で6人)で数人の感染患者が見られます。2025.06.08
熱中症について
奈良県では5月から熱中症が見られます。今年も5月中旬までに救急搬送された患者数が39人との報告があり昨年同時期の29人より10人増えました。3週間の入院治療を必要とする重症患者数も、現在3人(90代2人、70代1人)です。昨年は、5月の重症患者数はまだ0人でした。統計的には、熱中症患者数が急増するのは梅雨明け後の第一熱波到来時です。2025.06.01
熱中症について
奈良県では2022年から今年まで毎年5月に30℃を超えており熱中症の患者数も5月25日までで救急搬送された患者数は39人でそのうち重症患者は3人です。内訳は、お風呂の浴槽内1人、玄関口で意識障害が1人、屋外の物干しで意識障害が1人とのことでした。お風呂場は別として、重症例は昼間に発生しています。2025.06.01
伝染性紅斑について
現在、奈良県では定点当たりの患者数の報告で伝染性紅斑が第2位まで上がってきました。伝染性紅斑は、ウイルス性疾患で10日ほど前に風邪様症状がありその後頬に赤い発疹(リンゴのほっぺ)がみられ次に体全体にも発疹が出る疾患です。症状は、一般的には軽い症状で対処療法しかありません。ワクチンも今のところありません。ほっぺたが赤くなった頃には人にうつす感染力は低下しています。飛沫に注意です。胎児に影響が出ることもあるので妊婦さんは要注意となっています。2025.05.18
今年の熱中症について
奈良県内の今年の熱中症の始まりは5月3日(土)で、3人(軽症2人、重症1人)搬送されています。すべて男性で45歳以上の方でした。住居内1人、屋外2人です。重症の方は5月4日(日)95歳の方で高齢者施設内の浴槽で発見されています。2025.05.06
熱中症予防について
奈良県では、一昨年5月3日、昨年5月2日に最初の熱中症の救急搬送患者が発表されています。昨年の発表開始が5月初めでしたのでまだ今年は未発表ですがそろそろ注意が必要と考えます。奈良県の昨年の発表では、令和6年8月25日までの熱中症疑いを含めての救急搬送者は県内で1100人を超えており前の年より100人増えています。そのうち6割が65歳以上でした。対処として簡単な水分補給から始めてはどうでしょうか? 外出前に5℃~15℃の冷えた1リットルの水に食塩1~2g(小さじ3分の1)、砂糖20~40g(大さじ2~4杯)を加えたものを少し飲んで残りを持って出かけるのが良いと思います。また、5g程度の塩を小さなビニール袋に入れて財布の中にでも入れておくのも良いと思います。外出中に、見つけた自販機にアイスコーヒーやお茶や水やジュースといった塩分の入っていないものばかりしかないこともありますので念のために財布にでも入れておくと手軽で安心です。2025.04.20
熱中症について
昨年の奈良県内の初めての救急搬送熱中症患者は、5月3日でした。一昨年は、5月2日です。つまり近年、奈良県では、ゴールデンウイーク中に毎年熱中症で今年最初の救急搬送される方がいることに注意してください。重症の方はさすがに5月後半になって認めていますが一昨年では、市街地ではなく十津川村の80代の男性が5月21日に発見されています。熱中症で救急搬送される方のここ2~3年の傾向では、総人数では女性の方が多いですが重症患者数は男性の方が多いです。また、発生場所は、室内が最多でこれは冬の低体温症も同様で冬暖房をかけない、夏冷房かけないことが原因と考えられています。予防対策としては室内では年中18℃~28℃の範囲で過ごすことが大事です。2025.04.06
4月のヒノキ花粉症について
県土の77%が森林でそのうち約6割が人工林である奈良県ですがスギ、ヒノキ分布については約67%がスギで約42%がヒノキとの報告があります(奈良県林業統計)。その報告では奈良県の森林地区を大きく3つに分けて大和・木津川地区、吉野地区、北山・十津川地区となっておりスギに関しては、北山・十津川地区がスギの最大森林面積ですので注意が必要です。ヒノキに関しては、3つの地区はほぼ同じ面積となっています。ヒノキは例年4月の1か月ですので雨天日の前日から雨降る直前までを特に注意してください。2025.03.23
新型コロナ感染症入院患者数の動向
奈良県では今なお患者数2位の新型コロナ感染症ですが、入院患者数にも注目が必要です。3週間前には入院患者数28人で翌週23人でしたがまた先週49人と発表されました。内訳が不明なのですが2月の寒い時期にも48人となっていましたが今回は気温のせいというより介護施設等のクラスターがあったかもしれません。去年の最大患者数を記録した時期は、7月でしたのでインフルエンザのような季節に関連する疾患ではなくなったかもしれません。今年も去年同様、夏に流行ったなら従来冬の感染ウイルスとして分類されていたコロナウイルスでしたが季節よりも人ごみの方が重要な流行要因になっている可能性があります。2025.03.23
大黄砂の飛来
気象庁の情報では、3月25日(火)~26日(水)にかけて初めて大量の黄砂が日本に飛来するとのことです。27日(木)雨の予報ですので25日(火)以降雨の降る時までスギ花粉と黄砂が一体となって県内に飛散すると予想されます。2025.03.09
花粉状況について
3月12日(水)、13日(木)雨の予報ですので11日(火)から翌日雨の降る時刻までスギ花粉が大量に飛散する可能性があります。一旦雨が降り出したら飛散量が減少すると考えます。2025.02.24
低体温症について
低体温症とは、体の内側の温度(深部体温)が35℃未満になることで日常測る「わき」の温度でいうと34℃未満となります。症状としては震え、けいれん、強い寒さを感じ、呼吸が浅くなり肌が白くなりやがて意識がもうろうとして血圧が下がり始め心拍数が少なくなります。実は、厚生労働省の人口動態調査によると2013年から2023年の10年間で低体温症で亡くなった人は11852人、熱中症で同じ期間で亡くなった人は10395人ですので約1500人程低体温症で亡くなった人の方が多いのです。また7割は屋内で発症し8割が65歳以上8割が入院しています。室温が18℃以下になると急増するのですが冬の奈良県のリビングの平均室温が16.3℃、大阪16.7℃で、むしろ新潟18.4度、北海道19.8度!と比較すると西日本の方が低く最低室温は、香川県の13.1℃になっていました。対策は、暖房ですが夜間が一番最低になるのですから特に65歳以上の方は温湿度計を設置して20℃、50%で朝まで一晩中暖房、加湿器を切らずに就眠してください。2025.02.16
スギ花粉症の今年の飛散開始日について
今年のスギ飛散開始日は、2月11日(火)と考えます。理由は、翌日に症状の出た患者さんが多かったこと、翌日12日(水)が雨の日だったこと、5年前の飛散開始日が13日でこれまで徐々に繰り上がっていることです。2025.02.16
直近の奈良県感染症について
過去10年平均では、インフルエンザ感染症、新型コロナ感染症(過去5年)ともに最多患者数になるこの時期ですが現在インフルエンザでは3分の1,新型コロナ感染症では半分以下になっています。先週の奈良県の報告では最多患者数は、感染性胃腸炎で次にインフルエンザ、新型コロナ感染症の順です。原因は、よくわかっていませんが年末報道されていたとおり年末のインフルエンザ感染者数については例年の5倍以上になりましたので(新型コロナ感染症は、例年どおりでした)最多時期が年末に早まっただけとも言えますが一番寒いこの時期ではなく一番人口密度が多かった時期(年末の訪日旅行客や以前より年末にむしろ外出する人が多くなってきた)かも知れません。来年も同様になるか注意が必要です。2025.02.02
今年の花粉症について
2022年に閉鎖されましたが環境省のホームページに各都道府県の花粉数を毎時アップロードしていたサイトがありました。その報告では、ここ奈良県中部ではスギ飛散開始日が、2017年2月26日、2018年2月15日、2019年2月20日、2020年2月13日、2021年2月13日でした。また、お天気番組やネットの花粉サイトで「雨の翌日はスギの飛散が多い」とよく言われるのですが、その環境省の毎時発表されていたサイトで見る限りここ奈良県だけかもしれませんが雨の降る前日から直前までが特にスギ花粉飛散数が多くなり雨の当日や翌日はむしろ一気に減少します。この原因は、雨雲を動かす際に吹いている風が、花粉を飛散させるからだと推測されます。飛散後、道に落下した花粉は、土の多い奈良県では濡れた土に引っ付いてしばらくは再飛散しません。したがって例えば週の前半と後半に雨が降った場合などはその週の花粉量は減少します。反対に3日間晴天が続きさらに4日目も晴天ならばその4日目の花粉量は、一気に増えますので要注意です。常に週間天気予報を確認しましょう。2025.01.26
奈良県感染症情報
1月24日(金)奈良県感染症情報の発表では、多い順にインフルエンザ感染症、感染性胃腸炎、新型コロナ感染症となっています。インフルエンザ感染症は、先週と比較して約半数に減少し、新型コロナ感染症は約3分の1に減っています。ただしインフルエンザ感染症については、毎年2月上旬がピークで4月下旬には6位以下に減少していきますが新型コロナ感染症に関しては、2020年1月28日初めて奈良県内に陽性患者が判明したのち徐々に患者数が増え5位以内に入ってこの5年間今日まで一度も6位以下になったことはありません。しかも冬型ウイルスといわれていましたが昨年の最多患者数は、7月に記録しています。2025.01.03
2025年1月の奈良県感染症情報について
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さて昨年最後の2024年12月27日発表の奈良県感染症情報では、登録病院で1週間に前週18人から一気に増えて45人のインフルエンザ感染者が受診されていました。インフルエンザ警報もでています。皆様はいかがでしたでしょうか?インフルエンザに関してはワクチン接種率も全体では約30~40%程度と言われており一応の対処はできているように思われます。一方新型コロナに関しては、どちらかというと65歳以上の年齢別疾患と認識すべきと思います。65歳以上の方、又は基礎疾患をお持ちの方はやはり注意すべきと考えます。実際2023年5月~2024年4月までの1年間の新型コロナ感染者での死亡者数が約32000人でそのうち97%が65歳以上である。一方この同時期にインフルエンザ感染での死亡者数が約2200人であった。特に昨年1月~4月までに新型コロナ感染症で亡くなった方は14609人で同時期インフルエンザ感染では1156人で新型コロナ感染症の死亡者数が約12倍である点などに注目すべきと考えます。今回新型コロナワクチン接種率が11月初旬で納入量ベースで14%ですし、新型コロナ感染症に罹った際、内服薬としてゾコーバやラゲブリオ等がありますがその効果の弱さも少し問題になっており昨年10月中央社会保険医療協議会総会においても費用対効果が悪いということで薬価が下がる予定になっています。特に昨年正月明けから一気にインフルエンザ、新型コロナ感染症の両方とも患者数が激増し2月初旬にピークに達しました。年明けの両方の疾患の患者数に注意です。ちなみに奈良県感染症情報では、昨年末インフルエンザ感染者数は、1週間で2472人。新型コロナ感染者数は、180人と新型コロナ感染症患者数はインフルエンザの約13.7分の1ですが入院患者数は、インフルエンザ感染症が46人で新型コロナ感染者数は43人とわずか3人の差です。やはり新型コロナ感染症に注意が必要です。2024.12.22
12月20日(金)奈良県感染症情報
奈良県ではインフルエンザ感染症に対して注意報が発令されました。去年に比べて感染者数は、半分程度ですが先週から一気に2倍に増加しています。発熱していないインフルエンザ感染症の患者さんも受診されています。3位の新型コロナ感染症の患者数は、1位のインフルエンザ感染者数と比較すると6分の1ですが入院患者数は同じ29人です。60代以上の患者数もインフルエンザ感染症では全体の1割もいませんが新型コロナ感染症では3割以上が60歳以上となっています。入院患者の年齢分布は、発表されていませんが気になります。2024.12.16
奈良県感染症情報と新型コロナ感染症について
12月13日発表された奈良県感染症情報ではインフルエンザ感染症が1位となりました。新型コロナ感染症は3位のままでした。昨年のインフルエンザ感染者数はすさまじく年末では今年の5倍程度でしたのでまだあまり身近に感じないかもしれませんが人ごみに注意してください。それでも個人的には、やはり3位の新型コロナ感染症の感染者数が気になります。昨年の年末も今年同様夏以降徐々に減少し、インフルエンザ感染者数が一気に激増したためこのまま新型コロナ感染症は終息するように思ったのですが結局は、死亡者数2024年1月3911人、2月4569人、3月3623人、4月2506人で計14609人になりました。対してインフルエンザ感染症では、2024年正月より過去10年平均の約10倍の感染者数でしたが死亡者数は、2024年1月727人、2月260人、3月114人、4月55人で計1156人でした。もちろんどちらでお亡くなりになっても残念なのですが新型コロナ感染症での死亡者数は結局インフルエンザ感染症と比べて約12倍となっています。今年12月現在、昨年同様新型コロナ感染数は、少し減少気味ですが年初めに一気に激増したことを忘れずに年末楽しくお過ごしください。2024.12.09
奈良県感染症情報
12月6日(金)の奈良県の情報では、インフルエンザ感染症が2位に新型コロナ感染症が3位に上昇してきました。2024.12.01
奈良県感染者情報
11月29日発表の奈良県情報では、インフルエンザ患者数は昨年に比べて15分の1程度です。先週の感染症で多くなった患者さんの主症状は、鼻の奥に異常感が出現した後、のどがイガライ感じになり鼻水、咳がひどくなってきて来院される患者さんです。まず風邪かなと思ったら、温かい物、たとえばお湯、お茶の類を外出時も昼間水筒に入れてたびたび飲水するとか、昼飯を温かい麺類にするとか晩御飯をお鍋にするとか寝る前に温かいお湯を飲んでから就眠するとか寝室の室温を朝まで20℃、50%に保って寝るとか少しの工夫で悪化しにくくなると思います。先週、おひとり入院紹介しましたが急性扁桃周囲膿瘍という病気でした。これは体力の弱っている時に低温低湿の部屋で就眠するとなりやすいです。今年の夏もエアコンのドライモードで寝たり、エアコンの冷房と同時に扇風機をつけて寝たりして入院紹介になっています。2024.11.24
コロナ感染症とインフルエンザ感染症の年齢別発症率
奈良県感染症情報によるとインフルエンザ86人、新型コロナ感染症87人とほぼ同数の感染者数ですが年齢別では、インフルエンザ感染症では19歳までで60%で半分を超えており60歳以上では10%ですが新型コロナ感染症では19歳までで27%、60歳以上になると33%と新型コロナ感染症の方がインフルエンザ感染症と比べると3倍程度になります。現在のところでは、今なお高齢者に関しては、新型コロナ感染症の方がより注意が必要です。2024.11.17
2歳から19歳未満の方に対する鼻噴霧用インフルエンザワクチン
現在36の国と地域で承認されている経鼻弱毒生インフルエンザワクチンは、2003年に初めて米国で承認されています。小児にとってワクチンに伴う痛みは重大であり痛みの軽減を目的として考慮すべき方法と考えます。この冬に限定的に製造販売されることになり今年9月2日に日本小児科学会予防接種、感染症対策委員会から使用に関する考え方が発表されました。1)2歳から19歳未満に対して喘息患者には以前からの不活化ワクチンを推奨する。また授乳婦、周囲に免疫不全患者がいる場合は以前からの不活化ワクチンを推奨する。2)生後6か月~2歳未満、19歳以上、免疫不全患者、無脾症患者、妊婦、ミトコンドリア脳筋症患者、ゼラチンアレルギーを有する患者、中枢神経系の解剖学的バリアー破綻がある患者に対しては以前からの不活化ワクチンを推奨する。2024.11.10
60歳以上の新型コロナ感染症について(2)
昨年5月~今年4月までの1年間の新型コロナ感染症での死亡者数が約3万2000人でその97%が65歳以上であったことは前述しましたが重症化(酸素療法が必要な状態のこと)の因子として高齢者、男性、心血管疾患、脳血管疾患、慢性肺疾患、腎不全、透析、医師が診断した肥満、長期介護施設からの入院、身体活動状態の悪さが指摘されています。また60歳以上の重症化率は、インフルエンザ感染症の約4倍と発表されています。なお60歳以上の致死率も、インフルエンザに比べて約3.6倍となっています。(60歳未満なら新型コロナ感染症とインフルエンザ感染症と致死率は同じ0.01%です。)2024.11.10
60歳以上の新型コロナ感染症について(1)
現在、新型コロナ感染症の潜伏期は、平均5.2日、発症の2日程度前から他者への感染性がありこれは7~10日程度持続するといわれています。ちなみにインフルエンザの潜伏期は1~3日程度となっています。オミクロン株の症状は、鼻汁、頭痛、倦怠感、咽頭痛などの感冒様症状の方が多くなっており2020年ごろ味覚、嗅覚異常を訴える患者が多かったですが現在6分の1程度まで減少しています。むしろ鼻汁症状の方が約2倍に増えています。2024.10.27
奈良県感染症情報
10月25日(金)付の奈良県感染症情報では3週続けて新型コロナ感染症3位、インフルエンザ5位のままでした。新型コロナ感染症については、7月のピーク時から一気に減少しており(約10分の1)このまま減少していくと思いますが先日、報道で2023年5月~今年4月までの1年間で新型コロナ感染症の死亡者数が計3万2576人と発表されました。季節性インフルエンザとは約15倍の差(2244人)がありその97%が65歳以上でした。男性1万8168人、女性1万4408人でした。結局2022年死亡者数4万7638人、23年は3万8086人で新型コロナの報道時間は、激減しましたが死者数は9552人の差しかなく昨年の5月5類に移行してからも相当数の死亡者数が報告されています。現在、新型コロナ感染症は、65歳以上の方限定の注意すべき感染症となっています。2024.10.20
奈良県感染情報について
10月18日付けの奈良県感染情報についてインフルエンザが奈良県中部南部で上昇率が1位となり5位に登場しています。1才~80歳代まで患者さんがいますので全体に流行し始めたようです。入院患者も認めており注意が必要です。近畿全体でも定点当たり患者報告数では大阪を抜いて近畿でトップとなりました。2024.10.20
奈良県の気温について
昭和35年と今年の奈良県の8月の気温を比較してみると最高気温の平均について、昭和35年が31.7度、今年が35.0度でどちらも30度以上でした。最低気温は昭和35年が22.7度、今年が25.2度でした。当然今年の方が気温上昇しているのですが昭和35年では8月26日に最低気温が18.3度の日がありました。昭和35年ごろは、昼間が暑くても夜間には気温が下がっておりこの点が大きく違うように思います。2024.10.14
奈良県感染症情報
10月11日発表の感染者情報では奈良県でも初めてインフルエンザ感染者が多くなり患者数が5位になりました。年齢分布も1歳~80歳代までに及んでいます。当医院でも今週から発熱患者の方には、インフルエンザと新型コロナ感染症の同時定性検査を行うことになりました。また当医院でもインフルエンザワクチン接種しています。ちなみに現在奈良県のインフルエンザ感染者数は、大阪府に次いで2位となっています。2024.10.06
奈良県感染症情報について
奈良県では、多い感染者の順に手足口病、感染性胃腸炎、新型コロナ感染症,A群溶連菌感染症、RSウイルス感染症となっており新型コロナ感染症に関しては5週連続で減少しています。入院患者数も13人と先週24人から9人減少しています。一方インフルエンザ感染症での入院患者数が3人となりました。10月から定期接種が始まりましたのでワクチン接種も考慮して下さい。2024年10月からインフルエンザワクチンで注射でなく直接、鼻に噴霧する生ワクチン「フルミスト」が発売されました。2歳から18歳まで使用可となっていますが、今のところ自費となっています。2024.09.23
インフルエンザについて
今年も10月からインフルエンザワクチン接種開始となっています。昨年の感染症での死亡者数は上位から順に、新型コロナ感染、感染性胃腸炎、結核、インフルエンザとなっています。インフルエンザワクチンに関して香芝市では65歳以上で1500円。上牧町、広陵町では無料となっていますが新型コロナワクチンに関しては、香芝市は2000円、上牧町、広陵町は、3500円となっておりインフルエンザワクチンと新型コロナワクチンの両方接種した場合の合計額は同じとなります。2024.09.16
奈良県感染症情報と熱中症について
9月13日(金)発表の奈良県感染症情報によると初めて新型コロナ感染症が減少し2位に下がり手足口病が1位になりました。3週続けて新型コロナ感染症患者数が減少しています。熱中症に関しては県内で重症患者数が延べ18人となりました。9月に入っても2人認めています。香芝市内でも60代の男性がスーパーの駐車場にて39.9℃で意識が低下し接触事故で判明しています。2024.09.08
奈良県感染症情報
9月6日(金)に発表された奈良県感染症情報では、流行順に新型コロナ感染症、手足口病、感染性胃腸炎、A群溶連菌感染症、水痘症となっています。今回は初めて水痘症が上昇してきました。この1か月当院でも数人の方が受診されています。耳鼻咽喉科では、このヘルペスウイルスが原因で顔の表情筋が麻痺して目が閉じれなくなったり口から水がこぼれたりして初めて見つかることもあります。新型コロナ感染症については、ピークだった7月末に比べて約3分の1程度まで患者数が減少しています。2024.09.01
8月末の熱中症と感染症について
台風10号は、1日正午に熱帯低気圧(現在消滅)に変わりました。大事をとって8月31日(土)休診いたしました。ご迷惑をおかけいたしました。さて先週奈良県より発表された熱中症救急搬送状況によると、昨年に比べて123人増えており搬送者の割合では、男性で65歳以上の方が60%以上となっています。3週間程度入院が必要となる重症者の発症日は、必ず最高気温36℃以上の日となっていますので予想最高気温が36℃以上の日は、エアコンをかけて在宅しているのがよさそうです。2024.08.14
熱中症について(2)
今年の気温の上昇は異常で奈良県では今年と昨年の8月1日~12日までの平均最高気温を比較すると昨年は34.8℃、今年は36.2℃でした。とうとう体温と同じになってしまいました。そもそも体重60kgの人の場合、血管内には約3リットルの血液がありますが、夏場作業する前には塩分の入った水分(水1リットルに塩2g、砂糖20g)を取るようにしましょう。最近では運動後牛乳を飲むことも熱中症予防に効果があると言われています。2024.08.04
熱中症について
8月2日(金)に奈良県より発表された4月29日から7月28日までの熱中症患者数について679人となり、昨年同時期と比べて260人多く、そのうち65歳以上が65%、男性が65%、住居内が40%との事でした。2024.07.21
新型コロナ感染症について
7月19日(金)発表では新型コロナ感染症が手足口病を抜いて今週1位となりました。一気に10代、50代、80代が増加しました。先週10代が増加していましたのでその両親が感染されたのではないでしょうか。80代の増加は施設のクラスター発生と推測されます。昨年の同時期より増加しており入院数も37人(先週45人)で奈良県は、現在近畿内で定点当たりの患者数では大阪より多く最多となっています。2024.07.21
熱中症について
昨年の熱中症の統計報告を見ていて興味深いことがありました。昨年の熱中症の救急搬送数の統計で最多搬送数の都道府県は東京都でこれは納得なのですが最少搬送県が高知県でした。それから人口比もあり県内に観光等で訪れる人が熱中症になることもあり単純な数値の問題ではないのですが北海道の熱中症の患者数は3265人と沖縄の1059人の約3倍となっています。しかもその半分が住居内で発生していました。エアコン設置の有無かも知れません。また新潟県、宮城県が静岡県とほぼ同数で2100人で奈良県1182人の約2倍でした。発生場所が道路で1番少ない県が鳥取県と島根県でした(75人)。ちなみに奈良県では道路で211人で約3倍でした。2024.07.21
梅雨明けしました
7月21日(日)梅雨明けしました。ここから以下の事が、熱中症について重要となってきます。梅雨明け後の第1熱波の4日後くらいから急激に熱中症の患者数が激増する。その第1熱波による熱中症の患者が一番重症になる事が多い。その後、気温は8月になるにつれて上昇するが重症患者数は徐々に減少する。昨年、郡山市で70代の男性が畑内で熱中症のため死亡されましたが7月26日でした。当時最高気温36℃、梅雨明け7月16日でしたので梅雨明け10日後でした。ただし、奈良県では昨年の熱中症患者数1182人のうち4割が住居内で発生しています。2024.07.14
昨年度の職場における熱中症の発生状況について
昨年2023年の職場における熱中症死亡者数は1106人でこれは2018年の1178人に次ぐ多さでした。昨年の異常な高温多湿が原因と考えます。職業では、建設業、次に製造業でした。7月~8月が全体の8割を占めています。時間別では、熱中症患者数では11時台、14時台、15時台が多いのですが実は死亡率で見ると17時台(午後5時)が一番死亡率が高く6.6%となっています。職場で体調が悪く早めに帰って自宅で急変し病院に搬送されるケースです。ご家族で体調が悪い理由で早退された場合、なるべく一人にしないことが大事です。年齢別では50歳以上が約5割でした。2024.07.14
新型コロナ感染症
7月12日(金)奈良県発表では、新型コロナ感染症が手足口病に次ぎ第2位となりました。先週に続いて10代の患者数が上昇しておりこの世代が上がると両親もかかったりするので注意が必要です。上昇率も一番となっておりこのままいくと去年の8月のお盆の頃と同じ位の1週間に20人程度の感染者数になるかもしれません。2024.07.07
新型コロナ感染症について
奈良県内では先週に続いて現在3位の新型コロナ感染症ですが傾向として10代が増加してきており再びクラスターが発生している病院もあります。ちなみに国内で一番多く患者数が発生している県は、定点当たりの報告数では沖縄の29.91人で次に鹿児島の15.42人です。一番少ないのは、青森の1.81人です。2024.06.30
寝室でのエアコンの使い方
熱中症の発生場所として居間、リビングに次いで寝室が多く集合住宅では最上階が多い、寝室が西に面している場合が多い、という事がわかっています。また高齢者の熱中症の患者さんの大半は夜間のエアコンの利用頻度が低いという事もわかっています。ただし、一晩中エアコンを作動させるといわゆる「寝冷え」「冷房病」「クーラー病」になる可能性がありその初期症状はむしろ熱中症やコロナの初期症状にも近い為に対処が遅れることもあり頭が痛い所です。とりあえず8月末まではエアコンの寝室での使用はやむを得ないと考えます。ただし、「冷房病」等を防ぐために寝室に温度、湿度計を置き就眠1時間前に寝室の温湿度を計測しましょう。もしその時寝室の室温が31℃であっても就眠直前にはエアコンを使用して一気に温度23℃、湿度60%程度までに下げてしまいましょう。そのあと以下の3つの方法を考えます。1.タイマーをつけずに一旦エアコンを切る。それから就眠する。夜間暑くて目が覚めるならその都度29℃、最弱風で1時間後「切」タイマーに設定してエアコンを使用する。2.一旦エアコンを切る。次にタイマーの3時間後「入り」、4時間後「切り」を同時に設定して就眠3時間後電源が入って4時間後電源が切れるようにする。(つまり夜間暑くなることを想定して夜間1時間だけエアコンが自動に作動するように設定する。)その際も28℃~29℃、最弱風の設定をする。絶対に風量自動を使用しない。その後就眠する。ただしこれはエアコンによってはできない機種もあり昼間に実際に試してください。3.そのまま29℃、最弱風で一晩中つけておく。以上3つの方法を考えますが1は「寝冷え」にはならないと思いますが熱中症には用心しなくてはなりません。2は機種によっては不可能な場合もあります。3は熱中症にはなりませんが「寝冷え」にはなる可能性がありこれで当医院に受診される方が多いです。どの方法も冷風が直接特に顔に当たらないように気をつけて下さい。2024.06.23
奈良県熱中症について
奈良県の発表では、6月11日に2人の方が熱中症の重症となって救急搬送され入院となっています。一人は、70代の男性で明日香村の施設のサウナで発見されもう一人は、大和郡山の60代の男性で救急隊到着時、室温は高温状態で男性の体温も40.9℃との事でした。この日奈良県は最高気温31.1度でした。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前診 9:30〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 午後診 3:30〜7:30 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー |
土曜は午前9:30〜午後1:00まで診療
木曜と土曜の午後・日曜・祝日
インターネット・携帯電話順番受付時間
午前受付 9:05~12:00
午後受付 14:40~19:00
土曜日のみ 9:05~12:30まで受付
*当日診察のみの受付です
窓口直接受付時間
午前受付 9:00~12:30
午後受付 14:30~19:30
土曜日のみ 9:00〜13:00まで受付